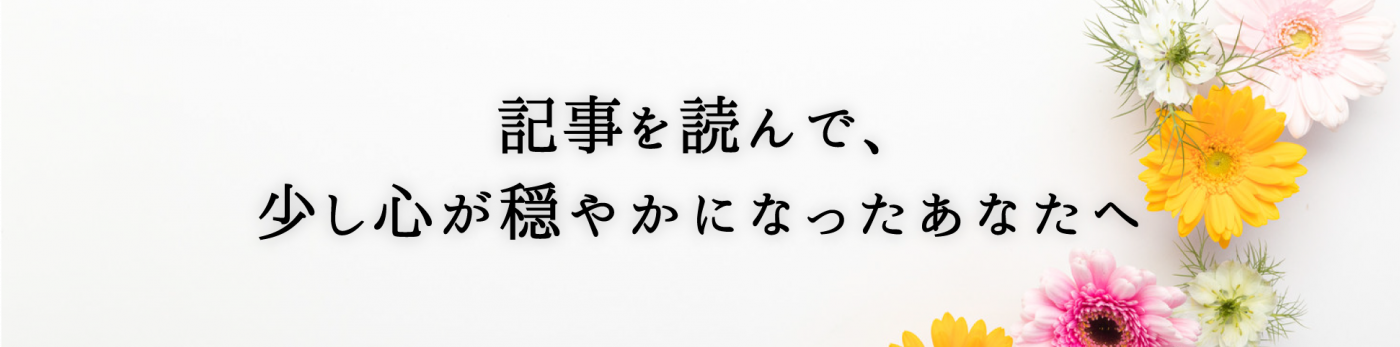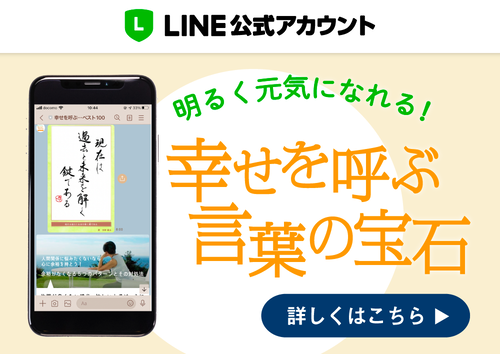他人の役に立てない人はいない|いつでも、どこでもできる親切とは

こんにちは。みさきです。
仏教の類のない心の洞察に感動し、学びはじめて5年になります。
「何か人の役に立てることができれば、生きがいを感じると思うのですが、私はお金もないし、資格も特技も能力もないので、人のために何かしたいと思っても、何もできないんです」という人があります。
誰にでもできる7つの親切がある
そんな人に、金も資格も特技も能力もない人でも、親切をしようという心さえあれば、人の喜ぶ七つの施(ほどこ)しができますよと、『雑宝蔵経』(ぞうほうぞうきょう)というお経に説かれています。
有名な無財の七施(むざいのしちせ)という教えです。
7つの中の「眼を与える」親切
無財の七施の一つ目に、「眼施(げんせ)」があります。
「眼を与えて」親切するということです。
無財の七施の中には、他に「言辞施(ごんじせ)」や「房舎施(ぼうしゃせ)」があります。
労いや優しい言葉をかける「言辞施」
一宿一飯の施しをする「房舎施」などは分かりやすいと思います。
でも「眼を与える」親切とは、どういうことなんでしょうか?
なぜ「眼」なのでしょうか。
「眼施(げんせ)」とは、優しい温かいまなざしで周囲の人々の心を明るくするように努めることです。
眼にたたえられた和やかな光は、どんなにか人々を慰(なぐさ)め励ますことでしょう。
特に心が敏感になっている時は、優しさが心に染みわたるようです。
友人の子供で、小学校4年生になる引っ込み思案の男の子が言っていたことを思い出しました。
「担任の高田先生は、いつもクラスのみんなを一人一人見て話しをしてくれるんだ。その目が優しくて、うれしそうな目で見てくれるから、話しやすい。高田先生は学校で人気者だ」
子供は、担任の先生のことをよく見ているものだなと感心しました。
その先生の優しい温かい眼差しから、子供たちは先生が自分のことを好きでいてくれる、信用してくれることを感じて、安心して話ができるんだと思います。
親切を行う時に最も重要なこと
「眼」は、おそらく「心」を一番表すところだと思います。
「眼は口よりも物を言う」とか、「眼は心の鏡」とも昔から言われます。
心を表す眼の慣用表現はいろいろあります。
「目が死んでいる」
死人の目であるかのように、うつろで覇気(はき)がないさま。
「瞳がキラキラ光る」
強い興味・関心を示しているさま。
「尖(とが)った目つき」
真剣で厳しいさま。
「目が泳ぐ」
隠しごとや後ろめたいことを指摘された時などに、心が動揺しているさま。
目ほど、心を表すところはないからでしょう、このような慣用表現はごまんとあります。
そうなると、「眼施(げんせ)」とは温かい心で真心を持って相手と接しなさいということになりますね。心は自ずと眼に表れるのですから。
仏教で教える親切の行為はその心にこそ重要な意味があるのです。
まとめ
誰でも、温かな心一つでできる親切が七つあります。
「無財の七施」と言われます。
「眼を施す」親切を勧められているのは、眼が何よりも心を映すからでしょう。
小さな親切が、与えた相手にとって大きな幸せの栄養源になるかもしれません。
みさき
最新記事 by みさき (全て見る)
- 友を見送り 自分の死を考える——仏教の智慧が心を軽くする - 2025年4月2日
- 「4つの間違い行動」を変えれば人間関係はグンっと良くなる - 2025年3月5日
- 認知症介護の悩みを軽くするために—心に寄り添うヒント - 2025年2月5日